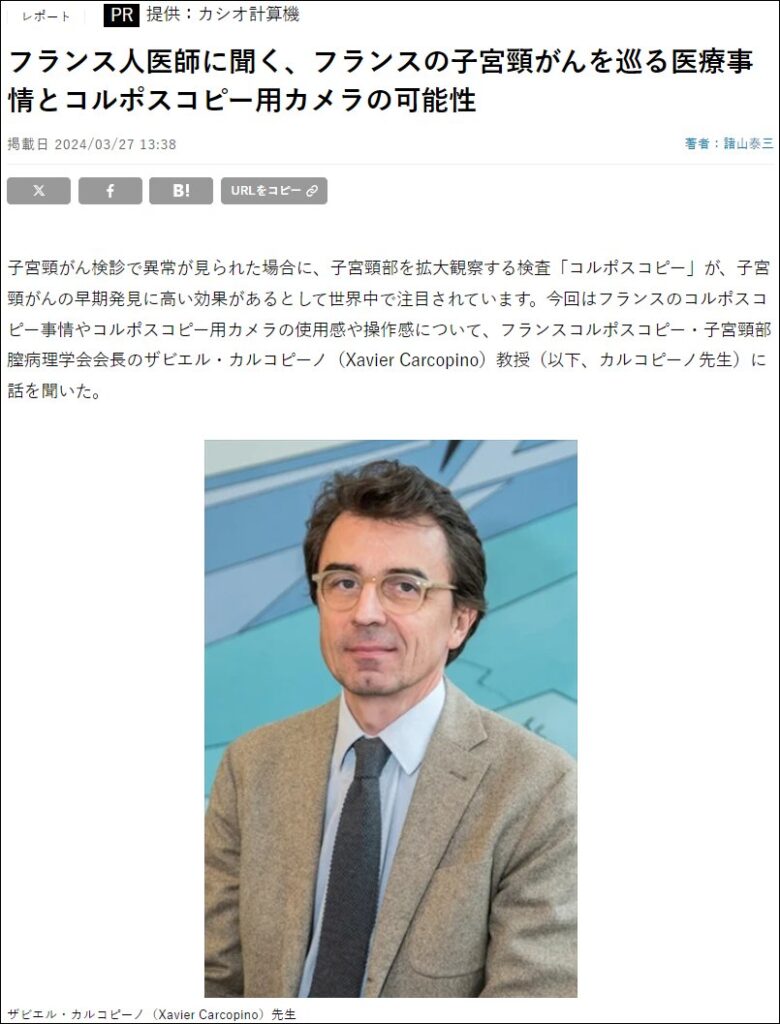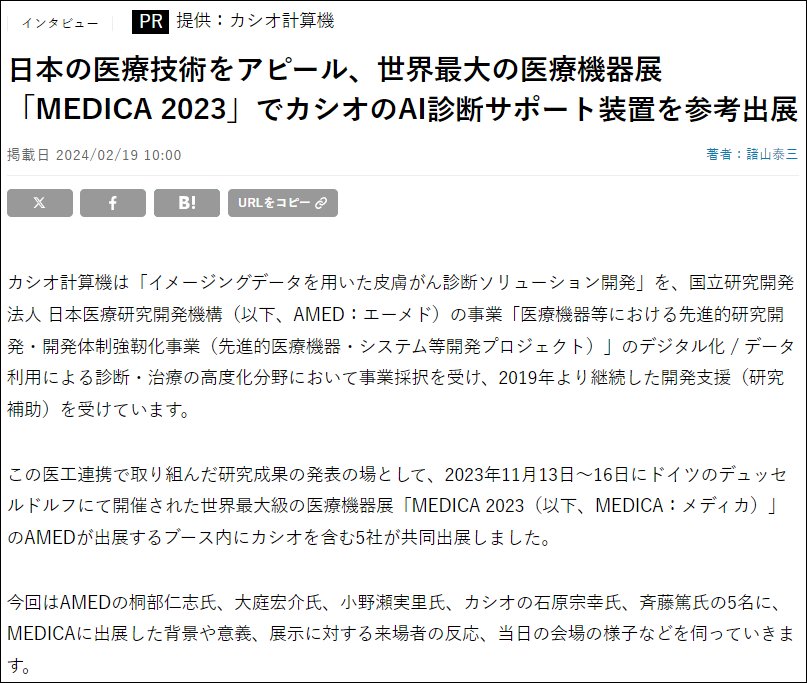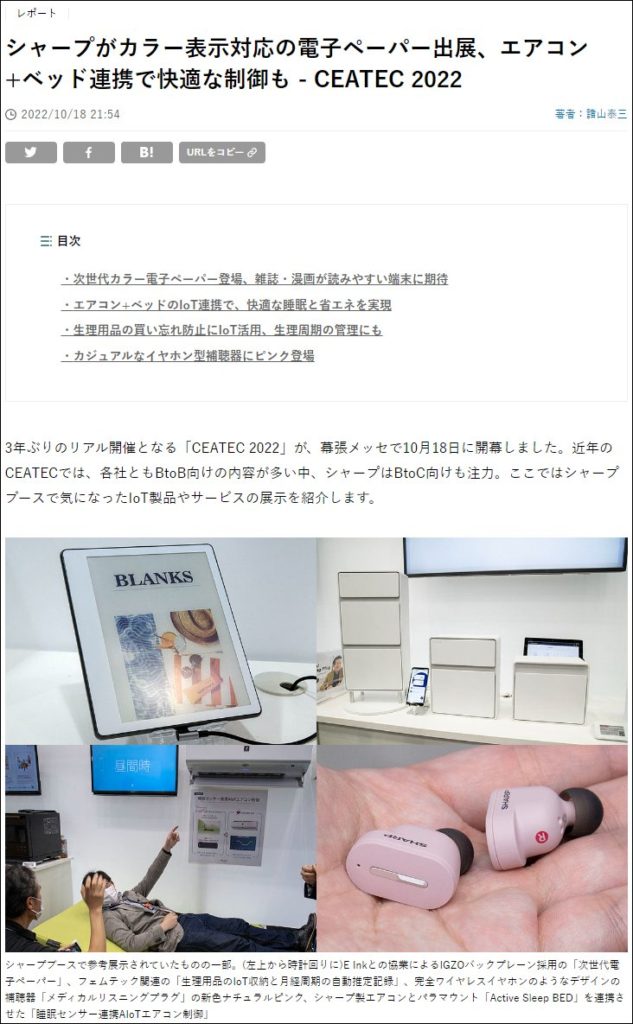フジ医療器さんの新製品発表会に出席しました。親会社であるジョンソンヘルステックさんが展開していた「SYNCA」ブランドを、フジ医療器さんで引き継いだもので、新製品はこのブランドの下、「CirC GRACE マッサージチェア L24 MR380(以下、L24 MR380)」の製品名で発売します。
本体カラーはベージュとブラックの2色から選択。5月1日の発売で、全国の家電量販店や同社直販サイト等で販売します。価格はオープン。想定価格は税込178,000円となっています。

SYNCAは「進化」や「真価」に由来し、高い機能性と洗練されたデザインとともに、上質で健康的なライフスタイルを提案するというコンセプトです。
シリーズ名となるCirC GRACEは、CirC(Circle)に「巣のように包み込む」の意味が込められており、GRACE(恵み)には「この製品の特徴的な優雅な曲線美」を表しているとのことです。

メインターゲットは30~40代のファミリー。同社の調査では30~40代でも日々の生活に疲れを感じている人は多く、身体的・精神的なケアへのニーズは高まっていると言います。実際のところ、自分自身が30~40代の頃を振り返っても、それなりに疲れが溜まってぐったりすることはありましたし、胃に穴が空きそうなこともあったことを思い出します。
L24 MR380の外観で目に付くのは、本体上部のアンビエントLEDライト。癒やしのブルーでくつろぎ空間を演出するとのことですが、人によっては落ち着かなくなりそう。そこはやはり、開発陣にもそう思う人がいたようで、ライトはオンオフ可能です。
両肩の位置には、Bluetoothスピーカーも搭載。ここから内蔵のヒーリングミュージックを再生できるほか、スマートフォンと連携して自分の好みの音楽も流せます。対応するBluetoothプロトコルは、A2DP V1.0/AVCTP V1.4/AVDTP V1.0/AVRCP V1.5/HFP V1.5/SPP V1.2/HID V1.0/GAP/GATT。対応コーデックはSBCとなっています。

L24 MR380が搭載するメカユニット「GRACEメカ」には揉み玉が4つ備わっています。上下約95cm、首や肩からお尻まで広範囲にマッサージでき、「もみ」「たたき」「さざなみ」「押しもみ」「指圧」のほか、緩急をつけた「リズムもみ」「リズムさざなみ」「リズムたたき」の8つのもみ技に対応します。
部位ごとのほか、全身と部位別に対応した5種類の自動コースがあり、コースを選択すると背もたれが自動でリクライニングする「ゼロフロートリクライニング」機能も備えています。
エアマッサージするフット部は、回転してフットレストになります。使わない時にはフットレストのほうがコンパクトになって邪魔にならないでしょう。エアマッサージは腰横にも用意していて、エアーの強さも4段階とオフから選べます。

操作部は右手側の腕部に埋め込まれていて、タッチとダイヤルで操作できます。ダイヤルが使いやすくて良かったです。

左の腕部にスマートフォンポケットがあるので、マッサージ中はスマホをそこに入れておけば不意の電話でも手に届く場所にあるので慌てずに済みます。ここまでするのであれば、いっそ操作パネルもスマホと連携していると、もっと便利に使えたかもしれませんね。

腰回りにはヒーターも搭載しています。熱伝導率の高いグラフェンヒーターを採用しており、実際に試してみると熱くなりすぎない印象で、冬場はもう少し温度が上がっても良いかもしれないと感じました。

先述のとおり、L24 MR380の価格は20万円弱と想定されています。これはマッサージチェアの中では安いほうで、同社のラインアップのボトムクラスは置き換わることになります。マッサージに毎月何度か通うような生活スタイルの人ならば、自宅で毎日使えるマッサージチェアの導入はコスト面でも十分に魅力ある選択肢ではないでしょうか。
L24 MR380はリビングにも個室にも、事務所にでも置けるポップなデザインです。このあたりもユーザーの若返りを意識していることが伺えます。とはいえ、マッサージチェア市場全体のメインユーザー層が60代以上なので、この製品もシニア世帯の購入はそれなりに多くなると見込んでいるそうです。
マッサージチェアは家電量販店で確かめてから買いたい家電の代表例で、メーカー販売員をどれだけ派遣するかがシェアに如実に影響を与えていました。昨今はこの傾向も薄れ、ネットで調べて店舗で確かめ、ネットで決済してしまうケースが増えているそう。店舗のショールーム化が進んでしまっているのですが、そうと分かっていても店舗に入れていかないわけにはいかないのが難しいところです。
ちなみにフジ医療器さんは、マッサージチェアを世界で初めて量産した企業として知られています。第1号機は「フジ自動マッサージ機」で、創業者の藤本信夫氏が1954年に製作。同社の創業年でもあります。2014年には日本機械学会の「機械遺産」のNo.68に認定されています。今年は同社の創立と第1号機発売から70周年の節目の年。注目の1年になりそうです。